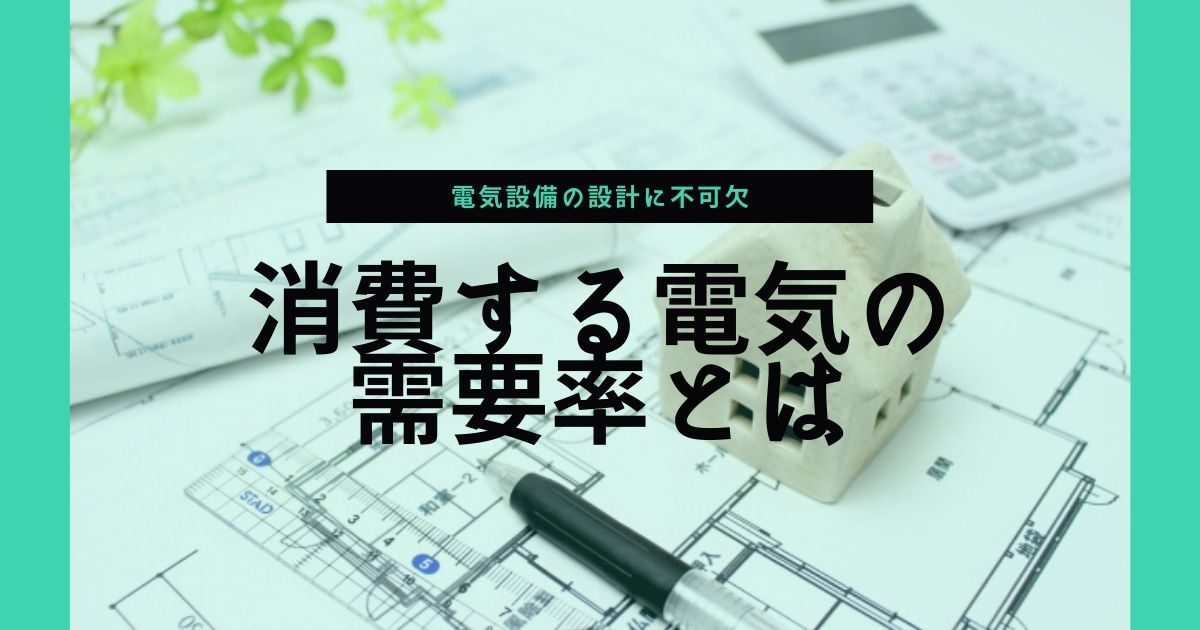スマホでアプリが普及した
こんにちは、今回の記事では電気設備工事をする上で役に立つ便利なアプリをご紹介していきたいと思います。
ここ7,8年の間でスマートフォンが普及して、誰もが持つようになったのでそれに伴って電気工事に役に立つアプリが使われるようになってきました。
施工管理に役立つものから簡単な調べ物ができるものまで色々とありますが、それらについてご紹介していきたいと思います。
時代はスマホ、いつまでもずっとガラケーなんかでは時代においていかれてしまうのでしっかりと付いていきましょう
現場で役立つアプリ
電気設備の施工をする上で今までに使ってみてとても役に立ったアプリをご紹介していきたいと思います。
もちろんここの挙げているものだけが全てではありませんので、色々と役に立ちそうなアプリを自分でもあsがしていってみましょう。
すぐわかる電力
このアプリは電気設備の設計を行う上で非常に計算が早く楽にできるようになる便利アプリです。
電気設備の施工を行うに当たり、使用する総電力量というのはきちんと計算をして算出していく必要があります。
その計算に必要になってくるのが電圧や電流、力率、電力などの値になってきます。
昔にやっていた方法としてはそれぞれの値を出しておいて、ひたすら関数電卓を叩きまくっていたのですが、このすぐわかる電力を使えば現場などでもさっと計算ができてしまいます。
電卓を使って必死に計算をしなくてもそういった数値が簡単に出るというのは非常に便利なアプリになります。
電圧降下君α
電気工事でたくさん計算をしなくてはいけないものの1つとして電圧降下の計算があるのですが、コチラについてもアプリを使用することで簡単に算出することができます。
配線の太さや長さ、電圧など必要な情報を入れることでケーブルで消費される電力や下がる電圧を計算することができるので非常に役に立ちます。
施工図を作成する際には各回路ごとに電圧低下が起こっていないかをきちんと計算で算出しておかなくてはなりません。
各回路ごとの消費電力を想定し、その消費電力で指定のケーブルに電流を流したときの計算をしていくのですが、電気の回路では決して1箇所で電力を消費するわけではなく、電力を消費する設備が点在してる状態なので同じ回路であっても流れる電流量が変わってきます。
そのため、計算は相当ややこしくなり、計算をするのも結構神経を使うのでかなり疲れていた記憶があります。
今では必要情報を入れるだけで簡単に数値を出すことができるので、とても便利です。
電線管サイズ教えて君
こちらのアプリでは名前の通り、電線管のサイズを教えてくれるアプリになります。
電線管の中というのは可能な限り配線を詰め込んでいいわけではありません。
たとえ電線を無理に入れられたりしたとしても、それでは不良工事なのです。
電線管の中に電線を通すときには、電線管の断面積に対してどのくらいまで電線やケーブルを入れてもいいのかといった決まりがあります。
そのようなことを知らずに勘で施工するタイプの作業員だった場合、必ずといっていいほど間違います。
電線管に入れることができるケーブルというのは思いのほか少ないものなのです。
電線の入れすぎが発覚すると場合によっては工事のやり直しなんてことも起こります。
なので、電線管のケーブルを入れる本数については気をつけたいところなのですが、その計算をやるとなると結構めんどくさいのが事実です。
そんな計算が簡単にできるようなっているアプリですので、現場で電線管を使用するときにはぜひ入れておきたいものですね。
照度計 ルクスメーター
こちらのアプリは手持ちのスマホが照度計になるという優れものです。
みなさんが持っているスマホのほとんどは明るさセンサーを搭載していて、そのセンサーによって外部の明るさを確認して、バックライトの明るさを調整してくれています。
このセンサーの性能を利用して、照度計として活用するのがこのアプリの特徴です。
照度計自体はそれほど高いものでもありませんが、こういった測定器具というのはいざ持ち歩くとなると結構面倒な荷物になるので、いざ照度を測定しようと決めて行くときでなれば持ち歩いていません。
急に照度を測らなくては行けないときなんかに、こういったアプリがあるととても役に立つのは間違いありません。
電気工事をやるなら入れておいて損はないと思います。
照度計アプリにはいくつも種類があるので自分にあった照度計アプリを探してみるのもいいでしょう。
電気工事の便利アプリまとめ
ここまで4つのアプリをご紹介してきましたが、知っているもの、既に持っているものなんかはありましたでしょうか。
どのアプリも電気工事を行う上では間違いなく役に立つアプリなので、入れておきましょう。
これ以外にも役に立つアプリはあるので、そういったものも活用して少しでも激務の電気設備の施工管理の仕事を短縮していくようにしていきましょう。