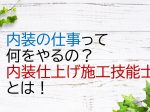建築士になるためには!一級建築士についてご紹介します。

建築物を建造する上で欠かせないのが、建物の設計ですよね。これが、建築士の手によって行われていることは広く知られているとは思いますが、建築士のその他の仕事についてはご存知でしょうか?今回は、建築士の仕事内容や、資格の取り方についてご紹介していきます。
建築士の種類
目次
さて、今回は一級建築士についてご紹介していきますが、建築士には他にも種類があります。
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
資格の種類によって、建てられる建物の大きさに制限があります。

一級建築士とは
一級建築士は、建物の設計や監理をする際に、その建物の高さや面積などに制限がありません。特に、他の2つの資格とちがって建てられる建物が以下の通りです。
・延べ面積が500㎡を超える一部の木造建築物
例:学校、病院、映画館、公会堂などの大型の建物
・延べ面積が300㎡を超え、タカさ13mまたは軒高9mを超える、以下の構造の建築物
これらは、二級建築士や木造建築士の資格だけでは取り扱うことができません。
一級建築士の仕事
建築士とは、一般的に建築士法という法律に基づいた国家資格です。建築士法の中で、建築士の仕事は「建築物に関し、工事監理その他の業務を行う者をいう」というように定められています。建築物の設計だけでなく、その設計通り工事が進んでいるかを現場で監理する仕事も含まれるということですね。もう少し詳しく、業務内容を見ていきましょう。
<建物の設計>
・基本設計
・実施設計
・意匠設計
・構造設計
・設備設計
設計というのは、建主の希望を叶えるだけでなく、構造や性能の部分も考えながら行っていきます。また、他の建物との兼ね合いなども、自治体の条例や法律などによって規制もありますから、そうした法的根拠を持って、建築位置などを調整していくわけです。
<工事監理の仕事>
図面が確定して、実際に工事が始まると、現場に赴いて自ら図面と実際の工事にズレがないかを確認していきます。
<手続きに関わる仕事>
上記業務だけだと、いかにも建築士!という感じがしますが、実際には手続きに関わる仕事が山のようにあります。まず、図面を引く前に土地の調査や規格などの業務があります。これを終え、図面の構成が進むのと同時に、工事に関する事務仕事や手続き関係の仕事が増えていきます。場合によっては、工事担当に指示を出すことも業務の一つですし、建主に代わって役所で手続きをすることもあります。このように、見えない手続きに関わる仕事というのが非常に多いのです。
建築士の仕事は多岐に渡りますから、製図に関する知識や技能はもちろんのこと、顧客とのコミュニケーション能力や営業能力、指示や監理ができる力なども求められることになるでしょう。
一級建築士の就職先
一級建築士は、以下のような場所で働くことが多いです。
・設計事務所
・ゼネコン
・ハウスメーカー
・工務店
・ディベロッパー
・フリーランス、個人事務所等
一級建築士は、先程からご説明している通り、業務内容も多岐に渡り、他の建築士の資格と比べて幅広い建物を取り扱うことができます。このため、専門的な知識や技能を持っていることの証明につながります。こうした資格を持っているだけで、就職や転職は他の建築士と比べてもしやすいというメリットがあります。また、普通に就職したとしても、手当や昇給などが期待できますね。
さらに、一級建築士の資格を持っていることで、その後経験を積むと構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の受検資格を得ることができます。これらの資格を取得することで、より仕事の幅は広がり年収アップも期待できます。
一級建築士の資格を取得するには
建築士の中でも一級建築士は業務範囲が広がるため、試験の難易度も上がります。このため、合格率は12%程度となっており、狭き門でもあります。しかしその分平均年収は高く、2019年のデータでは718.1万円となっています。
<受験資格>
この受験資格が少しややこしいので先に触れておきますと、平成20年に建築士法が改正されてからその改正前後で受験資格が異なります。特に、学歴要件のところは注意が必要ですので、しっかり確認するようにしましょう。
・大学卒業者で、指定科目を修了…卒業後の実務経験2年以上
・短大(3年制)卒業者で、指定科目を修了…卒業後の実務経験3年以上
・短大(2年制)・高専卒業者で、指定科目を修了…卒業後4年以上
・二級建築士…二級建築士として4年以上の実務経験
・建築設備士…建築設備士として4年以上の実務経験
・その他国土交通大臣が特に認める者…所定の年数以上
<試験内容>
学科試験⇒四肢択一式
設計製図の試験⇒あらかじめ公表される課題の建築物についての設計図書の作成
この試験では、まず学科の試験に合格しなければ製図の試験を受けられないようになっています。先程も申し上げた通り、合格率は12%程度なので、難易度が高いですが将来性や仕事の幅を広げることを考えると、挑戦することも視野に入れておきたい資格です。